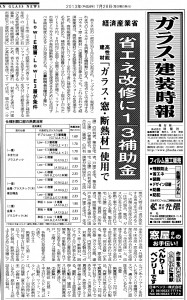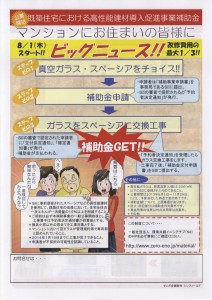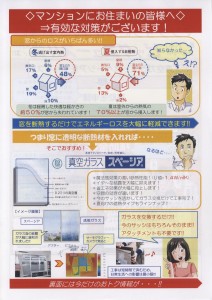3枚のガラスを貼り合わせた三重構造の合わせガラスを切断することになった。
真ん中のガラスは6㎜の強化ガラス表面両側はフロート5㎜で挟んであり、さてどうして切断しようかと悩むが真ん中の強化ガラスが装飾のためにわざとクラッシュされていたのが幸いだった。
ものはガラスのテーブルトップで、お客様は端の表面ガラスの割れた部分を切断して再利用したいとのご意向で、ダメ元で引受けた。
通常の合わせガラスは2枚構成なので裏面と表面からガラスカッターで切り筋を入れて切断するが、3枚構成の合わせガラスは真ん中のガラスに対してガラスカッターが使えないので悩んでしまうのである。
この様な場合は石を切断する様なダイヤモンドカッターで切断するのが一番手っ取り早い。
ガラス切断用のダイヤモンドカッターはあるにはあるが、ベビーサンダーに取付けてサンダーをフリーハンドで使用するのでモーターの振動や手振れの相乗で切断面にハマグリが多くなるので、あとの処理が面倒だ。
まっすぐ手振れなく切断するにはガイドレールにサンダーをセットすれば良いのだが、この1枚でその様な仕組みの工具を買うわけにもいかず、自作するわけにもいかないので、ある思いつきからフリーハンドで使う事にした。
その思いつきとは、先ずガラスカッターで切り筋を入れて、次に切り筋の裏からゴムハンマーで叩いて切り筋をクラックさせる。
次に裏返して同様の作業をすると、両面のガラスは切れているので次にその思いつきの核心を実行。
核心はクラックの外側つまり捨てる方のガラスにダイヤカッターを入れるとハマグリが入らずにダイヤがガラスを掻きだしてくれるので、裏表両面のガラスはガラス切りで切った断面が見えてくる。
実際にはダイヤカッターを入れたのは片面だけで合せのポリビニールブチラール膜も一緒に切っておいた。
あとは合わせガラスの切断要領で切れたのだが、真ん中のガラスがワザと割られた強化だったので思ったとおり切断断面に残る細片と抜ける細片に分かれた。
ガラス小口はフロート板がガラス切りで切断の断面と強化の小口は凸凹になっている。
60番のカーボンアランダムをディスクサンダーに取付けて凸の部分だけを削り落としていくと、かなり断面が平滑になった処で研磨ペーパーをロール回転する研磨機に取付けて研磨した。
加工メーカーのように艶出しとかは不可能だが、割れた部分の切断修復なのでこれで良しとするが、実際には加工メーカーでも強化ガラスの凹部分はどうにもならないので、強化部分のたどり着く仕上がりは一緒である。