日経ビジネスにワクワクするような記事が紹介されていたので、感じ取った思い等をかいつまんでみようと思います。
私は若い頃よりエネルギー問題には関心があり、リーマンショックの最中にやっと念願の太陽光発電3.6Kwを自宅に設置したのが、かれこれ5年前のこと。
以来、ますます省エネや再生エネに意識が向くようになりました。
いま沈滞ムードの日本ですが、エネルギー問題解決への秘めたるポテンシャルの高さは世界レベルでの技術力のようですが、もてざる国の宿命で特化したのだと読めました。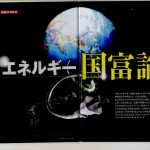
製鉄所がコークスの代替で水素を活用する動きや板ガラスメーカーがガラス溶融にプラズマを利用しようとした開発などは次の産業革命と位置つけても良い技術革新への前触れだと感じ取っています。
福島沖の浮体型風力発電のプロジェクトをみても1基で7000Kwの出力規模のものですし、蓄電池の開発には関連産業の総力をあげて突き進んでいるように思います。
自動車もEV化すると単に走らせるだけの電源ではなくスマートグリッドの発達で電力の調整役になる事は必須だと思いますし、そうでないと畜電池の使用が非効率になりますね。
既にNaイオン電池なども一昨年より実証試験段階に入っていますので今後が楽しみです。
http://eetimes.jp/ee/articles/1103/04/news120.html
天然ガスで発電用のガスタービンなどはその優れた効率から世界からの引き合いがあるようですし、同じ太陽のエネルギー活用でも光だけでなく熱も同時に取得しながら太陽を追尾しなくても朝から晩まで太陽エネルギーを取得できる装置なども開発されています。
バイオエネルギーも藻を活用したもので食料のトウモロコシを活用するよりはるかに効率的な事例が見いだされています。
あるいはまた地方自治体が独自で電源開発(ソーラー・小水力・その他)を推進し電力の自給化を図って実行している事などを見ると、この国で潜行しているイノベーションは産業の技術及び効率だけでなく東日本大震災以後、確実にしかも意識的に国土全体で始っているようにも思えます。
これらの技術が花開くとき、日本はもはやエネルギー小資源国とは言えなくなる様です。
それは世界中に対して高効率な省エネ・再生エネの中核となるシステムの提供が可能であるばかりでなく、そこに日本人が持つ国際貢献に対する精神文化も同時に発露するのではないでしょうか。
当店での太陽光発電がオール電化と共に導入した途端に激しい電気エネルギー低価格化に繋がりました。
システム導入前の電気・ガスの年間合計が100%として較べますと導入後に関電の買取り価格が48円/Kwhになってから年間の削減率は85.4%と驚くべき数字がでています。(平成20年導入前と導入後平成22年売電48円/Kwhとの比較)
具体的にはシステム導入前の電気・ガスの年間料金は約40万円でしたが導入後ガスがなくなり給湯も電気になっているのですが売電差し引き後の電気料金は年間約57600円で、年間の差額では34万円となっています。(風呂の給湯につきましては太陽熱温水器も併設していますので更に削減効果が高くなっています。)
そして今年は3月中の稼働を目指して吉野の実家で事業用で太陽光発電の設置に向けて動いています。
これは最低でも10.6Kwの出力が得られる屋根面に設置しますので年老いた無収入の父母には少しでも家計の助けになりますが、政府が決めた電力会社の買い取り価格は42円/Kwhで20年間固定ですから機器や屋根の改装費の償却には10年程度見ておけばよいとしています。
こうして当店で再生エネ(太陽光発電)や省エネ(真空ガラス スペーシア)等を導入しながら販売していく事で、社会に電気を融通して行く個々の規模は小さくても導入例が増えていくと少しでも冒頭のエネルギー国富に近づく事になりますし、時代のイノベーションを更に促進する事に繋がると思います。
